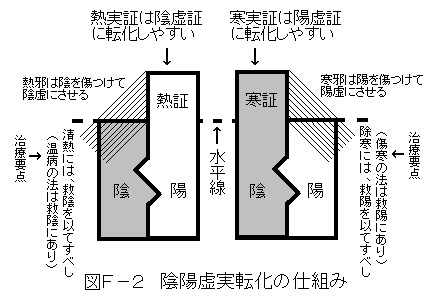気化について
人の生きるということは、漢方医学的に考えると気、血、水(津液)が有機的にからみ合い運行することによって進行している。この気、血、水の中で私達はともすると実際目に見える物質としての血、水の研究のみに多くの時間をさいてきた。少なくとも現代医学での気に関しての範囲は比較的せまい。
しかし、よく考えてみると気というものがなかったら、血液や水分もそれぞれ単なる血の固まり(死血)や水たまりになってしまう。人の呼吸、心臓の鼓動、飲食したものを消化する、全身に血液や水分を行らせる、歩く、のもすべて目に見えない実感できない何者か、すなわち気というものの働きが原動力となってエネルギーを生み出している。
漢方でいう気とは、人体における各臓腑、組織の活動力のもとになるものである。化とは、その気を動かし変化させ転化させることである。
漢方でいう気化とは、体内にある各種の気の運動、変化、転化というエネルギーの一連の動きのことで、目に見えないけれど途方もない力の存在、これが私達人間も含めて生きとし生きるもの万物の生命の根源ということができる。
気化の過程では、陰陽の対立、相互依存、相互促進、相互制約を行って発展、運動、変化して、目に見えない無形の推移を繰り返している。このエネルギーのことを陽気と呼んでいる。
またこの陽気の力で演変を繰り返して目に見える有形の物質が作られる。この作られる物質を陰気と呼んでいる。この物質は陰で、陰気というものは陰の背中に気が載っている状態で、エネルギーとなる気を背負ったいつでも運行している生きた陰である。
気と血と水の関係は、各個が孤立しているのではなく、互いに連携し助け合ってはじめてその機能を発揮できる。
陽気は単独ではその力を発揮できず、血や水がなかったなら寄り付くものがなく、中に浮いてフワフワとあてどもなく漂い、その力の補給の道が断たれて減退し、いつの間にかに消えてしまう。
また血や水は、陽気が背中に載っていないと陽気の補給がとだえ、血や水を発展成長させる陰気が次第に減少してしまい、それぞれ単なる血の固まりや水たまりとなって、物質、形体の発展成長は止まってしまう。このように気、血、水は互いに助け合って人体の発展成長を推進している。
陽気と陰気は休むことなく変化を繰り返し、対立的統一の運動の過程を経て物質の源泉となり、一切の事物の生成、発展の根本となっている。
この過程を要約すると次のようになる。
気化
┌───┐
│ 気 │
・陽気 ──→ 陰気 ─├───┤
気化 │ 陰 │
└───┘
・陽気+陰気 ──→ 陰(物質)−形体 ──→ 発展・生長
気化
人体を形づくっている気、血、水の関係についてもう少し述べると、昔から気については色々の表現がある。気力をふりしぼる、気が抜ける、気が通じる、気を落とす、気をはく、気を取り直す、気迫、気つけ薬、気ばる、気弱、気が切れる、気がはる等々である。
マラソンでフラフラになりながら気力をふりしぼってゴールした途端に倒れ込むというのは、肉体の血も水も使い果たして、少し残っている気だけで血や水を引っ張っていったものです。ゴールした途端にその気もいっぺんに抜けて倒れ込んでしまったのです。
野球の投手が気迫を込めて投げる球は、滅多に打たれるものではありません。その球は切れが出て手元でのび、まるで生きているように見えます。ちょうど球に力が乗り移ったかのようです。これは球という物体に目に見えないすごい気のエネルギーが乗り移っているのです。
入院患者の臨終の際、陰である補液による営養物(水谷の精微)の補給や酸素吸入(天陽の気)によって生きている人間が息が途切れて死ぬのは、陽の気が途絶えることに他なりません。自然衰退あるいは破壊によって「命門の火」が消滅すれば、どれほど天陽の気、水谷の精微を補給しても、「生」というものに見放されて「死」が決定的なものになります。気は生命を左右する力です。
いま脳死の問題が色々と騒がれているが、このような漢方医学の考え方からすると、人の「死」というものは下にある腎の命門の火が消えることにほかならない。
古人は「人の生は気の聚なり。聚まれば生れ、散ずれば死す」。また張景岳は「それ生化の道は気を以て本となす。天地万物これによらざるはなし・・・四時万物生長と収蔵を以てす、すべて気のなす所なり、人の生はすべてこの気に頼る」といっている。
以上の文からも分かるように気は人体の生命物質の基礎で、また人体各種機能活動の動力で、気化は人体の生長、発育の根本となるものであるといっている。
気化とは、これらの物質が相互に化生し、相互に転化するエネルギーを出す過程、とりもなおさず生命活動であり、このエネルギーを出す「動」にほかならない。
人体の内は五臓六腑から、外は身体全体、経絡のいたる所みな気が存在し気化作用を受けている。気の働きの昇降出入、上下内外、至らない所なく、人体の生命活動はすべてこの気の運転に頼っている。
気が充実すれば体は健康であり、気が衰えると体は弱くなり、気が落ち着いておれば身体も精神状態も平穏で、気逆するといろんな疾病が生ずる。このように気化作用は生命の原動力である。
もちろん、血液の運行、精気の転輸、津液の輸布、食物の消化、営養の吸収、糟粕の排泄、筋骨の濡潤、皮膚の温煦<オンク>(温める作用)、毛髪の光沢、及び臓腑の調和などはすべて気化に頼っている。
気化が休みなく続くことによって生命を保っており、気化が止まると生命も終わってしまう。
気化の作用によって外邪への抵抗力もつくし、自然環境の変化にも順応でき、成長発育していくことができる。
気化の原動力
人体を工場にたとえると、工場を動かす動力つまり電力が必要である。人体にはその電力を作りだす発電所が三ヶ所ある。一番重要な最初の発電所は、地中のマグマからの絶えることのない補給による燃える腎の命門の火つまり先天の気である。次いで、肺にある風力、ソーラーによって天陽の精気を取り入れて電気を起こしている。これは命門の火の気化を助ける。最後に、石炭(飲食物)を原料として人工的に電力を得、絶えず命門の火と胸中の宗気の消耗した分を補充し、縁の下の力持ち的役割を果たしている水谷の精微から得られる後天の気である。この三ヶ所の稼働によって工場(人体)は休みなく動いている。
命門の火(先天の気)
張景岳は「命門は精血の海、脾胃は水谷の海であり、いずれも五臓六腑の根本である。命門は元気の根であり、五臓の陰気があっても陽気がなかったら、その機能を発揮して各臓腑を滋養することはできない。脾胃の気は、下の腎中の命門の火つまり腎陽の火の力の補給を受けて腐熟、運化を行っている。したがって下の命門の火は脾胃の母ということができる」といっている。
命門の火は人体の生命の原動力、先天の火の根、後天の火の源である。命門の火は元気の根本、元気を発揮する最初の推動力である。いわゆる「腎は先天の本となす」とは一つは腎は精を蔵し(先天の精と後天の精を包括する)生命活動の物質的基礎になるものであり、もう一つは命門の火のことで生命活動の原動力を指す。
生命の過程中、命門の火は気化機能を推動していると同時に絶えず消耗されており、腎精も絶えず転化し消耗しているが反面これも補充を受けている。胸中の宗気
胸中の宗気は水谷の精微の気と、自然界の大気が一緒になって胸中に聚ってでき、呼吸作用や心臓の拍動によって精神活動や全身を活発にし、気化の一動力となっている。
これも気化作用中は絶えず消耗されているので、水谷の精微の気と天陽の気によって補充されている。水谷の精微(後天の気)
第三の気ともいわれているもので、飲食物から脾胃の腐熟、吸収によって得られるものである。第一の命門の火、第二の宗気を常に補充して生命活動を維持している。
この水谷の精微(後天の気)を作りだす脾胃の作用は、また先天の気(命門の火)の力に頼っている。
気化のシステム(図F−1)
古代の医家達は「天人相い応ず」という理論で、自然界の現象の気の昇降を用いて人体の生命活動を解釈してきた。
《素問・陰陽応象大論》に「地気上りて雲となり、天気下りて雨となる。雨、地気より出で、雲、天気より出づ」とあり、昇降出入(上下内外)の運動は天地万物の生化の根源であるといっている。人体の生命活動も例外でなく、この二つの昇降出入が基本となっている。
陰陽五行学説によれば、この昇降出入の運動は陽浮陰沈、陽降陰昇、水昇火降というように表されている。
陰陽五行では相互に対立し、また統一的矛盾をはらみながらこのような昇降出入を繰り返し営んでいる。もしこのような昇降出入の運動が失速すると陰と陽は静止し孤立してしまい、自然に生命活動も止まる。
陰陽五行は漢方医学での一種の理論であるが、臓象学説もまたこの理論の核心であり、その中の昇降出入の運動機能は、相互促進、相互制約し、協調して生命活動を営んでいる。
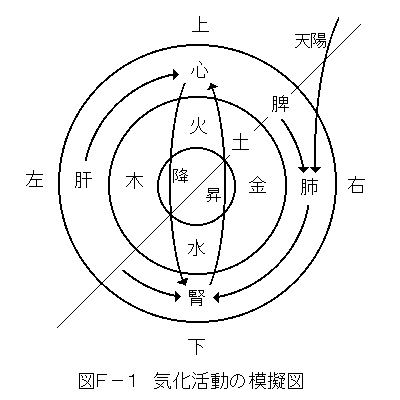
気の運行時の臓腑における昇降出入の運動を簡単に述べる。
臓腑の気の運化は各臓腑機能の絶ゆみない昇降出入の運動に頼っている。脾気は昇を主り、水谷の精気を肺に上輸し、肺は華蓋であるので肺気は降を主り、水谷の精気は天陽の気と一緒になって下降し、各臓腑に輸送されている。肝気は昇を主っているので、陽気を頭顔部や上半身に輸送している。腎気は降を主り肺を助けて天陽の気を納め(呼吸作用)、また一方では真気を下降させ下半身に輸送している。
その他、胃気や大腸、小腸、膀胱の気はいずれも降を主り、水液や糟粕を下方に伝送し、最後に糞尿として体外に排出している。
臓腑の気の昇降はこのように順序がはっきりしており、協調と平衡を保って各種生理機能を行い、人体の生命活動を維持している。
脾胃は昇降の中軸である
清・呉達の《医学求是》の中に「脾は陰土で陽を昇し、胃は陽土で陰を降す。土は中に位置し、火は上り水は下り、左は木(肝)、右は金(肺)、左は昇を主り右は降を主る。五行の昇降気を以てし質を以てせず、昇降は中気によって左右される。昇は脾気の左旋に頼り、降は胃気の右転に頼っている。したがって中気旺んなれば脾は昇し胃は降し、木、金、火、水みな輸転し、中気の流れがよどめば脾は鬱し胃は逆し、木、金、火、水みな運行を失する」とある。
ここでは脾胃は昇降の中軸であると述べている。
脾胃は後天の本、気血生化の源、臓腑経絡、全身すべてにわたり水谷精微の運化によって気血を化成して、全身に輸布し営養している。
肝肺の昇降の輸転に依存しているとはいっても、脾胃は昇降の中軸であり、重要な中枢的役割を果たしている。肝肺は昇降の外輪である
葉天士は次のように述べている。「人身の気の機能は天地自然と融合し、肝は左より昇り、肺は右より降り、昇降宜しきを得れば気の働きは伸展す。人身の精気の輸布、流行は肝肺が重要な鍵となっている。肝は昇って頭部や上竅(目、耳、鼻、口)に上達し、肺は降って臓腑や筋骨に下達し、気血はよく流れて臓腑は安泰である」。
肝は下焦に位置し、肺は華蓋となって上焦に位置し、肝は昇り、肺は降って廻りながら運行すれば、気の機能はよく暢び、気血はよく流行して臓腑の働きは自然と安泰で身体もすこやかになる。心腎は昇降の根本である
心は君主の官といわれ生命を主っており、腎は先天の本であり精を蔵して生命を営んでいく上でなくてはならないものである。また心は火臓(心は五行では火)、腎は水臓(腎は五行では水)、水は陰、火は陽に属している。昇降は陰陽の運動であり、臓腑の昇降の運動は心腎が根本になっている。水火の昇降のしくみは複雑で、昔から多くの人が論述している。
その中で《呉医彙講》には「心は火臓で火中に水あり、腎は水臓で水中に火あり(心陽−火、心陰−水、腎陰−水、腎陽−火)」とある。
火は水の主であるので、心気は下交しようとするし、水は火の源であるので腎気は上に昇ろうとする。水が昇らないと病になるが、腎の陽を調整すると腎の陽が充足され、水気は腎陽すなわち腎気に従って昇っていく。火が降らないと病になるが、心の陰を滋すと陰気が充足されて、火気は心陽すなわち心気に従って降っていく(心腎相交)」とある。わかり易く説明すると次のようになる。
心は火に属し上に位置し、常に火のために熱を帯び乾燥し易い。つまり火−陽のために乾燥して水−陰が不足し、炎天の砂漠と化し易い。火(陽)は益々勢いを増し、心火上亢となって一尽の熱風が舞い上がる。
また腎は水に属し下に位置し、水が溢れ洪水になる傾向がある。つまり腎の陰−水が溢れて洪水を起こし、大地は水浸しになる。心は陰の量的減少によって砂漠化の傾向、腎は陰の量的過剰によって洪水化の傾向になる。
心腎の昇降運動は、心の陰陽の平衡状態と腎の陰陽の平衡状態が必須条件となる。心腎の陰陽の割合がたとえば5:5すなわち平衡でなければ気化の根本の心腎の昇降は起こり得ない。
砂漠に水をやり乾燥した大地を潤せば、上昇気流の熱風つまり心火上亢も止む。また溢れた洪水の大地を太陽の熱(心陽→腎陽)で乾かし、ちょうどよい湿り気の状態にすることによってはじめて昇降運動の条件が整い、スムーズに心腎間の昇降が行われ、正常な臓腑の機能が発揮される。
また張景岳は「火性はもと熱、火に水なければその熱必ず極まる、熱、極まれば亡陰、而して万物焦枯す。水性はもと寒、水中に火なければその寒必ず盛す、寒甚しければ亡陽、而して万物寂滅す」と。
以上でもわかるように水火相い済けるという現象は正常な人体の生命活動の原点であり、水火の昇降相済は生命の存亡を左右する。
漢方の臓象学説の臓腑と現代医学の臓器とは全く異なる。
たとえば漢方医学中に出てくる臓象学説での左肝右肺という考え方は、現代医学の解剖学的位置や器官からすると似ても似つかぬもので理解に苦しむ。しかし漢方医学中の臓象学説での左肝右肺という考え方は、気の運行や昇降の理論を説明したもので、二者を一概に解剖学的角度から比較することはできない。
また水火相い済けるという考え方は、漢方医学での臓腑機能の活動の矛盾、対立、統一という一種のしくみであって、それなりに理解することができる。
2.傷寒と温病<ウンビョウ>
傷寒と温病は、外感病における異なった概念であるが、これらの間は密接に関係している。晋・唐以前はまだ温病学説が独立した形態の学説として確立しておらず、一切の外感熱病は広い意味の傷寒に含まれ傷寒と総称されていた。
《内経》に「熱病はみな傷寒の類なり」とある。
明・清の時代になって温病学説が興り、次第に傷寒の域から離れ独自の体系を確立するに至り、従来までの傷寒に含まれるという形から、傷寒と温病の関係は各々対等の立場で論じられるようになった。その結果、温病の範囲が拡大し、外感熱病だけでなく各種熱病の総称となり、傷寒の範囲は狭くなり単に風寒で起こる一連の外感病に限られるようになった。
つまり、温病学が形成される前は傷寒の意味は広く使われ、温病学が形成された後は、傷寒から離れて広く温病という概念が用いられるようになった。
このような概念の変化は漢方医学での外感熱病の認識を変え、以後の漢方医学の発展に大いに寄与している。
風寒でひき起こされる傷寒と、風熱でひき起こされる温病とは、同じく外感病に属し、はじめはいずれも表証がみられるが、その病因も証候も治療方法も異なっているので、臨床でははっきりと区別して考えなければならない。
| 傷寒 | 温病 | |
|---|---|---|
| 病因 | 風寒 | 風熱 |
| 病 | ・寒邪が表に留恋後、熱と化して裏に入る ・寒によって陰凝、陽を傷つけ易い |
・熱邪で起こるが、表証は短い ・伝変が速い ・温は陽邪、陰を傷つけ易い |
| 証候 | ・発熱 ・悪寒 ・熱軽く ・寒重い ・身痛 ・無汗 ・舌苔白 ・舌質正常 ・脈浮緊 |
・発熱重い ・悪寒軽い ・口渇 ・舌苔白 ・舌辺尖紅 ・脈浮数<サク>(早い) |
3.陰陽虚実の転化(図F−2)
陰陽学説によれば陰陽は相互に転化できるという法則があり、また虚実の二証も転化することができる。それではどのようにして転化するのだろうか?
熱邪は陰を傷つけ易いので、陰が傷ついた結果転じて陰虚の証となる。陰陽学説中のこの理論は臨床面において指導的役割を果たしており、古人は次のような語句で表現している。
「傷寒の法は救陽することであり、温病の法は救陰することである」。これは傷寒と温病の二大類を治療する上での重要な原則となっている。