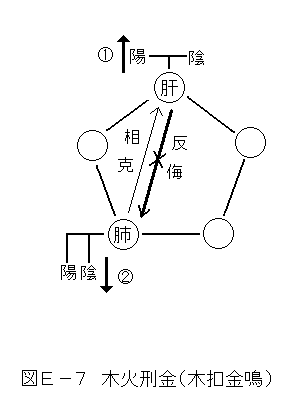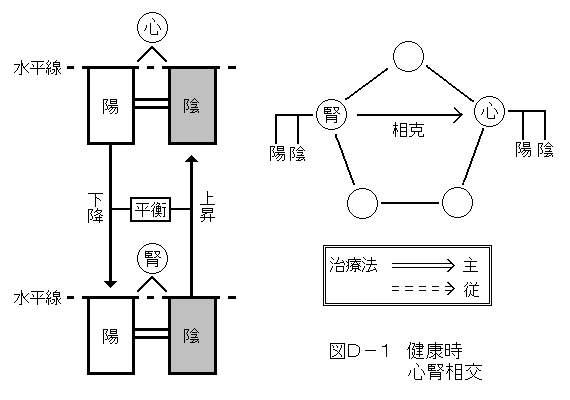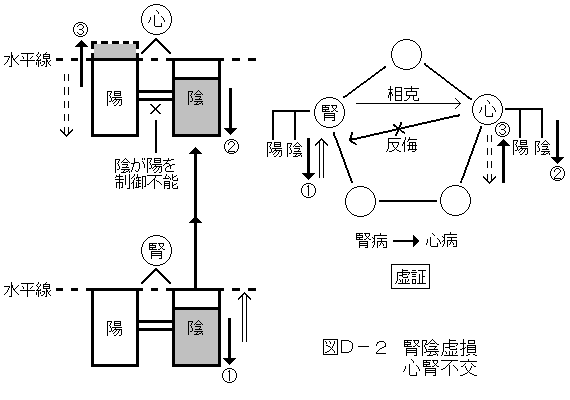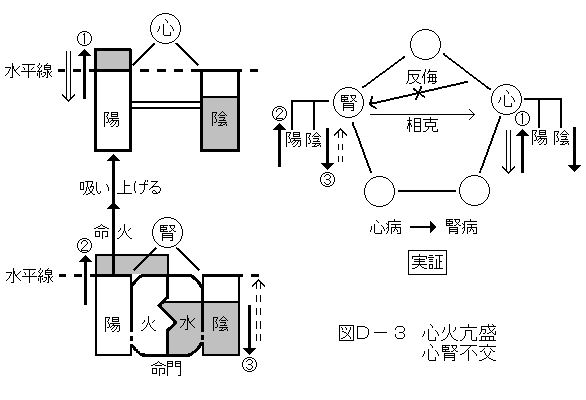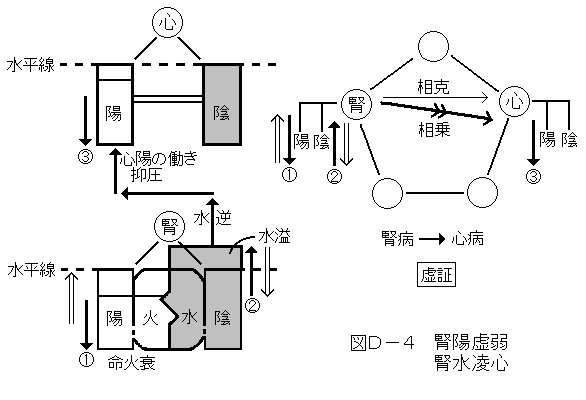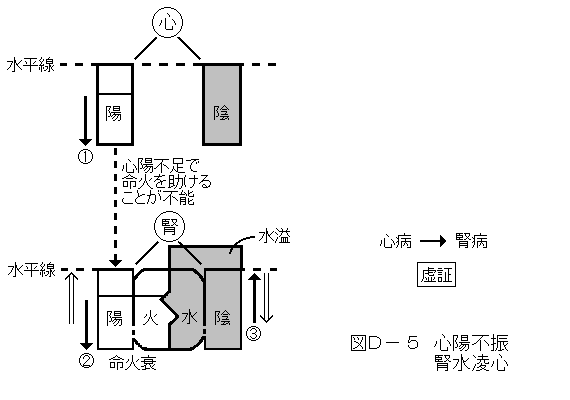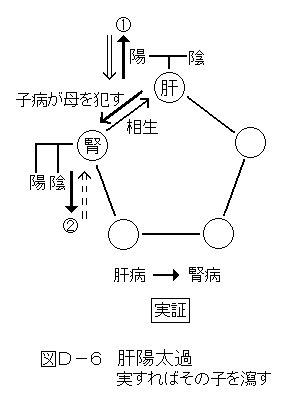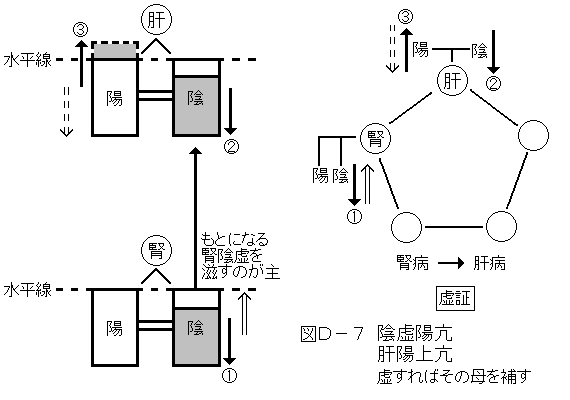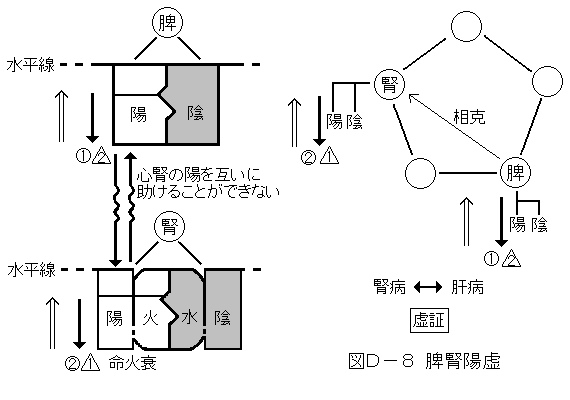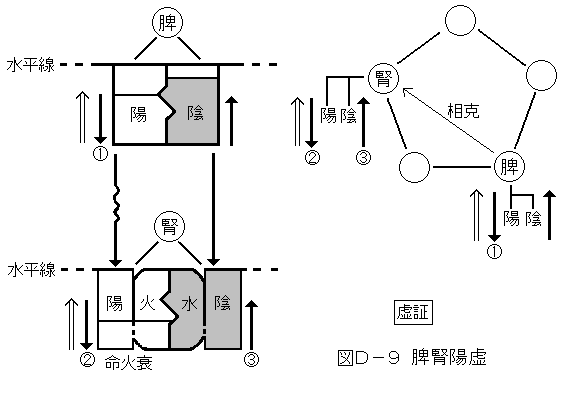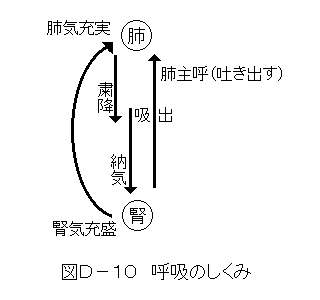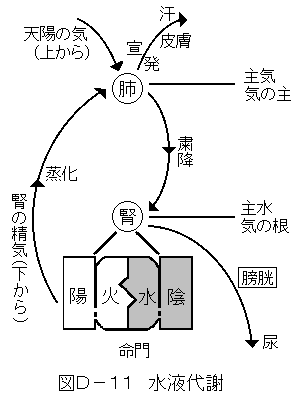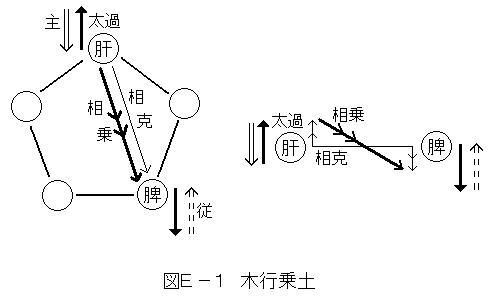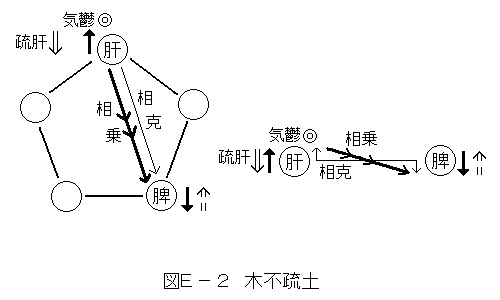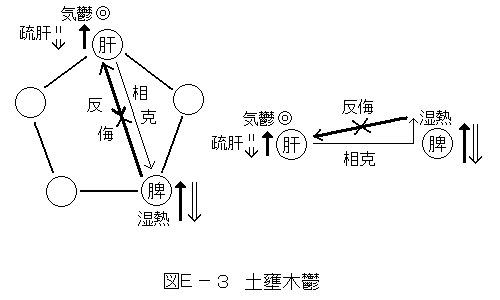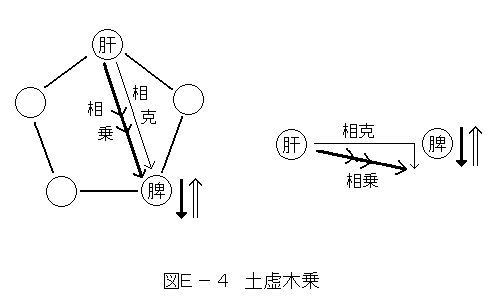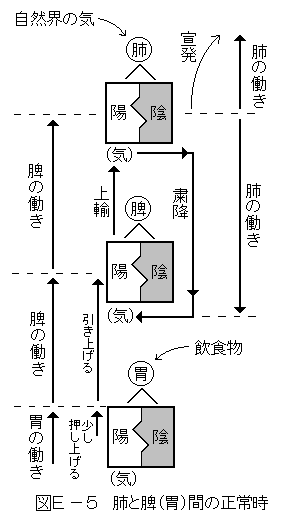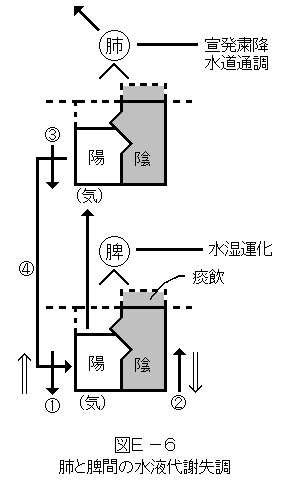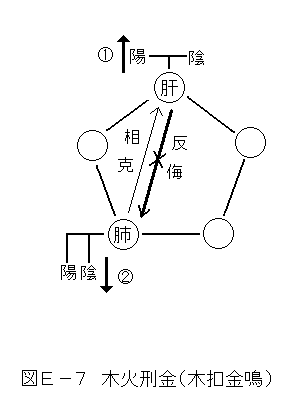五臓間の関係
人の生命は、臓腑の働きの密接な連係、相互協調また相互制約と対立により、発展と運動を繰り返して、複雑な生理活動を営んでいる。
疾病の複雑で錯綜した発病メカニズムの中で、その発生、発展、変化をもとに、どの臓腑で起こった疾病なのかを確定することは、先ず第一にとりかからなければならないことである。
現代風にいえば、病院を選ぶ際の何科に行ったらよいか、一応の目安をつけることとよく似ている。要するに疾病の個所の確定である。その場合単純に一臓あるいは一腑のときもあるが、往々にして多臓腑にまたがることが多い。
これら臓腑の間には、依存と制約の過程で、平衡と不均衡、相互転化が起こり、五臓間の太過と不及という関係が生ずる。そして相互的平衡がくずれて太過や不及が起こると、疾病が発生し、複雑な証候を呈する。これら複雑な証候を五臓間の規律、つまり陰陽五行学説の相生、相克の関係などを利用して認識し帰類していくことは、疾病の本質を知ると同時に、疾病の治療の上で最も重要なことである。
1.心と腎
心腎相交(図D−1)
心は上焦にあり陽に属し、腎は下焦にあり陰に属している。心は火を主り、腎は水を主っている。心と腎の間は昇降関係によって、互いに陰陽助け合い、生理上平衡を保っている。心中の陽は腎に下交して腎陽を温養し、腎中の陰は心に上昇して心陰を滋養し、陰陽水火は相互に昇降し、協調し合って動的平衡を保っている。これを「心腎相交」という。
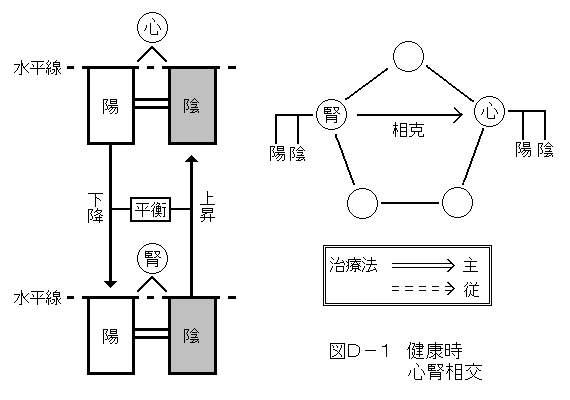
腎陰虚↓ ─→ 心火亢盛↑(図D−2)
腎陰が虚損し、上昇して心陽を滋養できなくなると、心陽は腎陰の制約を受けることができなくなって心火が亢盛し、いらいら、動悸、不眠などの証候が現れる。
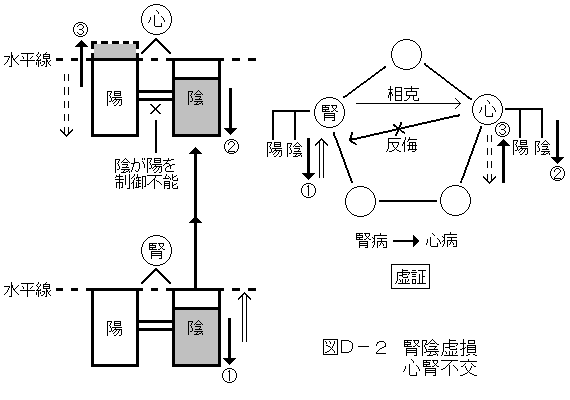
心火亢盛↑ ─→ 腎陰虚↓(図D−3)
また心火が亢盛し、腎に下交できなくなると、かえって命門の火を吸い上げることになり、いらいら、不眠、夢精、滑精、腰酸痛(腰のだるさや痛み)が現れ、いわゆる「心腎不交」となる。
この場合、上焦の心火が上亢すると、上昇気流ならぬ力が働いて下焦の命門の火を吸い上げ、メラメラと命火が燃え上がり、その結果腎の陰が虚し、ますます心火が上炎するという結果になる。
腎陰が虚損して心火が亢盛した場合は、腎病が心に累を及ぼし、主な矛盾は腎にあるので、腎陰を補う治療法でもってしなければならない。この場合病は心病に属する。
心火が亢盛して命火が妄動し、その結果腎陰が虚損する場合は、心病が腎に累を及ぼしたもので、主な矛盾は心にあり、心火を清して下降させなければならない。この場合は心自身の病である。
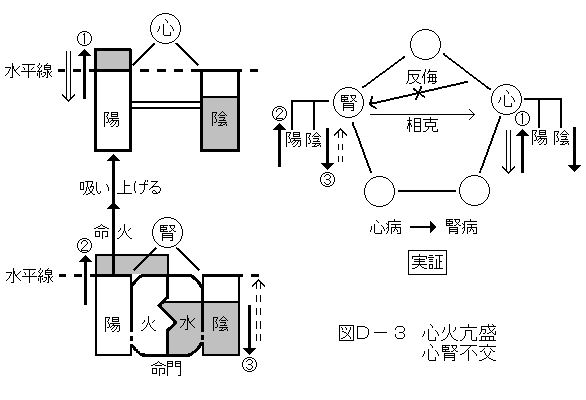
腎陽虚↓ ─→ 心陽虚↓(図D−4)
腎陽が不足し必然的に腎気も不足し、水門の開閉がうまくいかず、水門を開いて水分を膀胱に下行させることができず、水分が一杯になって上に溢れ水飲内停し、上の心陽の働きを阻害し、「腎水凌心」(水が溢れて腎陰盛になり、心の働きを抑圧して心陽虚になる)を起こす。命門の火の衰えによって、全身(各臓腑)の陽気が低下し寒が生じる。
腎陽虚↓ ─→ 命火衰↓ ─→ 腎陰盛↑ ─→ 心陽虚↓で陰盛が心に乗じるような恰好、つまり相乗になって心を害する。症状としては心悸、咳喘、四肢寒冷、小便不利、浮腫などが起こる。この場合は心病の虚証に属する。
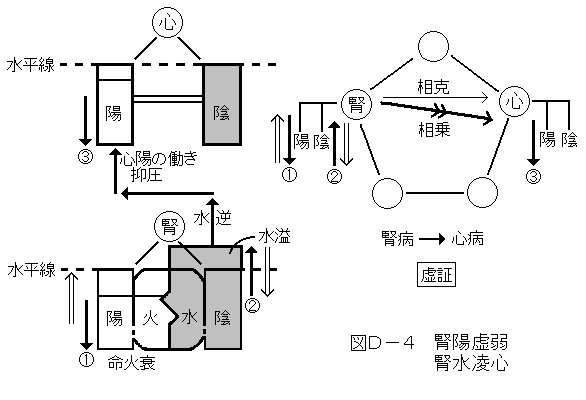
心陽不足↓ ─→ 腎陰盛↑(図D−5)
心陽不足では、心陽が下降して腎陽(命火)を助けることができず、腎陽不足(命火衰)を起こす。その結果腎陰盛(水溢)になる。そして腎陽虚↓─→ 心陽虚↓の場合と同じく「腎水凌心」が起こり、同じような症状が生じる。この場合は心自身の病で虚証に属する。
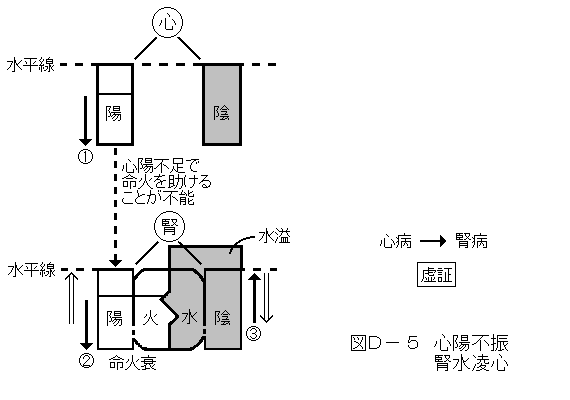
2.肝と腎
腎は精を蔵し、肝は血を蔵する。肝と腎の関係は主に精と血の関係である。肝血は腎精の滋養に依存しており、肝の疎泄と血液の調節機能は、これによって順調に営まれている。肝血が充盛すると血は化して精となり、腎精もそれにつれて充実することができる。腎精が虚損すると肝血不足をきたし、肝血が不足すれば腎精も虚損することになる。
肝腎二臓は、一方が盛んになるともう一方も盛んになり、一方が衰えるともう一方も衰え、運命共同体であり、そのことから「肝腎同源」といわれている。肝と腎は二人三脚のようなもので、どちらかが転ぶと片方もそれにつれて転ぶ。肝と腎は五行学説からいえば「相生」の関係にある。
肝陽太過↑(図D−6)
肝の陽(火)が太過になって、母である腎の陰(水)を損耗させる。子病が母を犯し、肝病が腎病をひき起こすことになる。この場合は肝病に属し実証である。
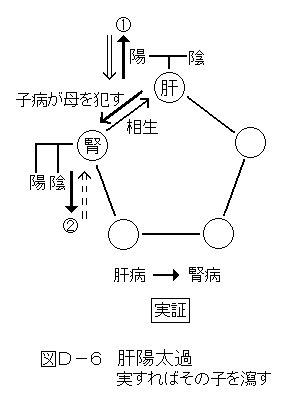
腎陰太過↑
腎陰太過は腎陰盛、水が溢れた状態で寒が生じる。寒が生じた結果、気の流れが滞り気滞が起こる。肝寒の発生は、次の四つの場合がある。
- 外邪によるもの
- 気滞のよるもの
- 肝陽不足によるもの
- 血淤によるもの
腎陰太過では、気滞によって肝寒が生じる。
腎陰太過 ─→ 寒生 ─→ 気滞 ─→ 肝寒
五行学説でいえば、母病が子に及ぶことになり、腎病が肝に及び、この場合は腎病の実証である。
肝腎はともに下焦にあり、肝陰、肝陽、腎陰、腎陽の間は互いに制約し合っている。もし一方が不足すると別の一方が偏亢し、また一方が偏亢すると別の一方が不足する。たとえば腎陰不足では肝陰不足をひき起こし、その結果陰が陽を制御できなくなり、肝陽上亢になる。また反対に肝陽が妄動すると、腎陰を襲い腎陰不足が起こる。(図D−7)
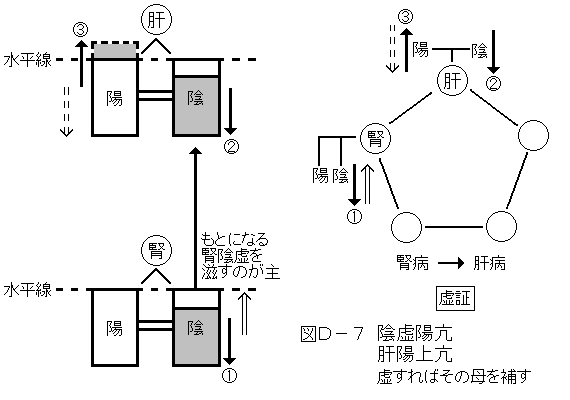
3.脾と腎
脾は「後天の本」、腎は「先天の本」といわれており、両者の間には密接な関係がある。先天不足になると後天に影響が及び、後天不足では先天が不利となる。
臨床上この二臓は、不足すなわち虚弱の傾向になることが多い。脾の運化機能は腎陽の温養に依存しており、腎陽が充実しておれば脾の運化機能もすこやかであり、脾陽が充足しておれば水谷の精微や水湿を十分運化できる。この場合腎陽が不足すれば、それにつれて脾陽不振をきたし、運化の機能が失調する。反対に脾の運化機能が失調すると、腎陽の働きを活発にする源泉が枯渇し、腎は後天の脾の助けがなくなり、腎虚が出現する。(図D−8)結果的に脾腎陽虚となる。
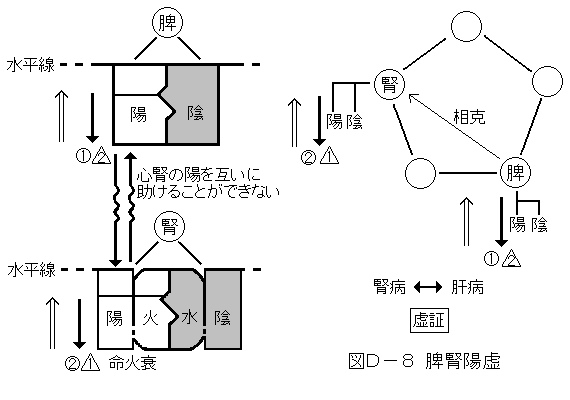
脾陽虚になって水湿内停すると、腎虚とくに腎気虚になり、腎の気化作用が失調し、水門の開閉がうまくいかなくて、水湿が内停し浮腫や飲となる。(図D−9)
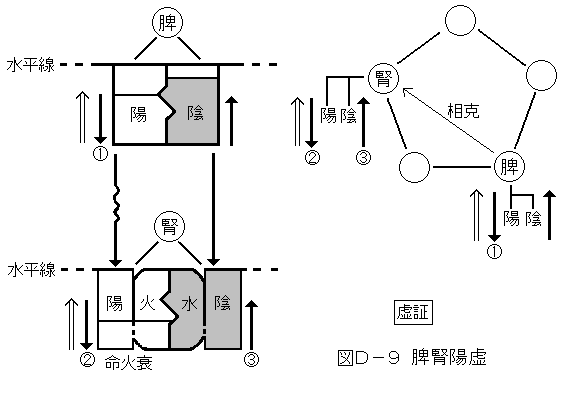
このようなことを五行学説では「土、水を制せず」といい、脾と腎の間の「相克」関係がくずれた状態である。臨床上よくみられる「五更泄<ゴコウセツ>(毎朝、明けがたの腸鳴下痢)」は、腎陽虚(命火不足)によるものである。
4.肺と腎
肺は気を主りかつまた粛降を主り、水道を通調する。腎は納気を主り水の臓であり、一身の水液代謝を管理している。
呼吸(図D−10)
呼吸は肺と腎との協同作用で行っている。腎気が充盛すると、吸い込む力が強くなり、また肺気も充実して肺の粛降作用も強くなる。肺は呼吸を司っているので、吐き出す力もスムーズに働く。
腎気が不足すると、呼吸の吸入する力が弱く、呼多く、吸少なくなって呼吸が浅く、気は下降して行かず上浮し、喘息などの病証が現れる。
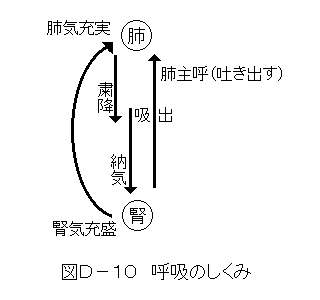
水液代謝(図D−11)
肺は一身の気を主り、水の上源で、腎は一身の水を主り、水臓である。水液は肺の宣発粛降の作用によって人体各組織に送られ、膀胱に下輸される。腎は水液の気化昇降の機能をもち、また水門開閉の役目を行っている。
肺と腎は水液代謝にあって重要な役割を果たしており、その中のどれか一臓の機能が失調し病変が起こると、別の一臓に影響を及ぼす。たとえば水腫の病人で喘して臥することもできないのは肺と関係があるが、その根本は腎にある。
また尿がでないのは、腎だけの責任ではない。肺気の宣発、通調(粛降)作用の失調とも関係がある。
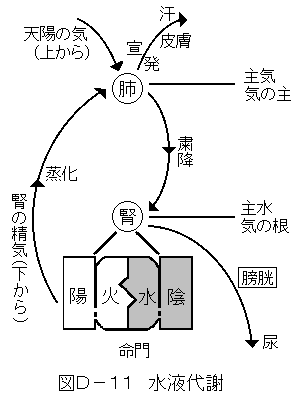
肺陰不足
肺腎の間は五行学説でいえば、母子の関係である。肺陰虚になると腎陰また虚す。陰虚では燥熱の象となる。「虚すればその母を補す」ということで肺陰を滋しかつ生津(津液を補う)をもってしなければならない。肺陰虚で久病の結核などの病人は、肺腎両虚になり、咳喘のほか腰膝酸軟、遺精、閉経などの症がみられる。
5.心と脾
心は血を主り、脾は血を生じ血を統べ、両者はみな血と関係がある。血液は、脾の水谷の精微を運化する働きによって生化する。
脾気虚になると運化機能が失調し、脾の生化の源泉が不足し心血不足になる。いわゆる「土虚火衰」である。そうして心脾両虚になる。これは脾病が心に影響を及ぼしたことになる。
また心陽の不足は脾の運化機能の失調をきたす。脾の機能が正常であれば血を統括する作用を発揮できるが、脾気虚になると統血ができず妄行し出血する。このように心が脾に影響を及ぼした状態を「火、土を生せず」といっている。心脾の機能が失調すると、出血ばかりか淤血の症も出現する。
以上の場合臨床上、動悸、健忘、不眠、食欲不振、出血、月経不順などの症状がある。
6.肝と脾(胃)
肝は血を蔵し疎泄を主り、脾は血を生じ運化を主り、肝と脾の間の主な関係は疎泄と運化である。肝の疎泄作用が伸びやかで気の通りがよい状態では、脾の運化機能も正常に発揮される。肝の蔵している血は、脾の水谷精微物質の運化に頼っており、脾の運化が不良になると肝の疎泄がうまくいかなかったり肝血不足を起こす。また反対に脾の運化は、肝の疎泄作用に依存している。
《金匱要略》に「肝の病を見れば、肝、脾に伝わるを知る。まさに先ず脾を実せしむべし」とある。これは病を治す場合だけでなく、積極的予防の意味も兼ねている。
肝の疎泄太過(木横克土)(図E−1)
肝の作用が亢進し肝気の太強、疎泄が太過になり横逆し、脾土に乗じて脾の機能が弱くなる。肝気が脾胃を横逆し、肝木が脾土に乗じ直接脾胃を傷つけるので、胸脇、胃腹痛及び脾胃の症状がはげしい。
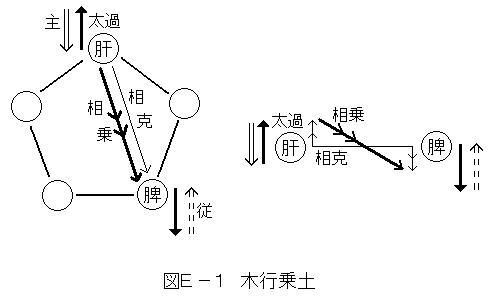
肝の疎泄不及(肝気鬱結)(図E−2)
a の肝の疎泄太過とは程度が異なり、肝気鬱結によって気滞を起こし(虚ではない)、肝木が脾土を疎泄できず、間接的に脾胃の機能に影響を与える。この場合、脾胃本身の機能の損傷は比較的軽い。肝気鬱結では、肝気脾を犯す場合(肝脾不和)と肝気胃を犯す場合(肝胃不和)の二通りがある。
肝気鬱結から肝気太過になって脾胃を横逆することはあるが、すでに肝気横逆したものが肝気鬱結に転化することはない。
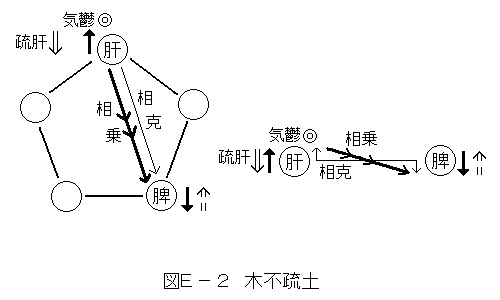
脾胃湿熱(肝胆湿熱)(図E−3)
脾胃湿熱 ←→ 肝胆湿熱
黄疸がこれである。脾湿胃熱、湿熱がからみ合って胆汁と結合し、胆管から皮膚に溢れて黄色くなる。
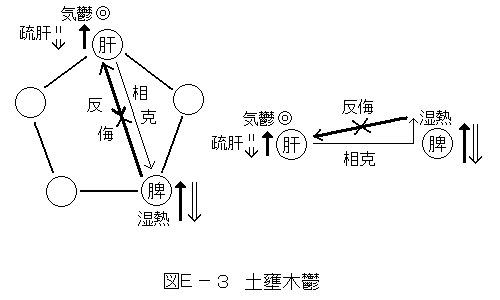
脾虚肝乗(図E−4)
前にあげた肝気鬱結により肝脾不和をきたすのとは異なり、気滞という実はなく虚の場合である。この場合は腹部拘攣痛の症状が現れる。
培土抑木の法で治療する。
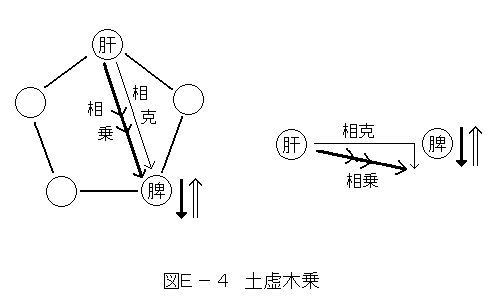
7.肺と脾(胃)(図E−5)
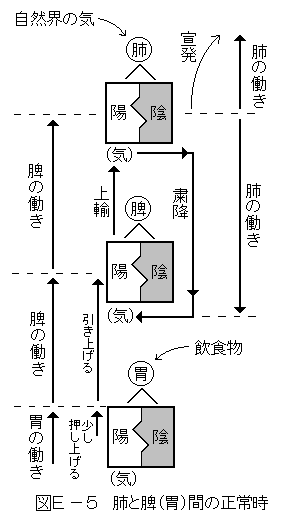
肺と脾(胃)の関係は、気と水液代謝の二方面が主なものである。
気に関して
肺は気を主り、脾は気を益する。肺は呼吸によって自然界の清気を吸入し、脾は輸化によって飲食物から化生した精気を肺に上輸し、二者協同して宗気を作っている。肺気の充盛は後天の水谷の精気の休むことのない補充に依存している。したがって肺気の盛衰は、脾気の強弱の如何で決定される。
つまり、脾は肺の益気作用を助けている。肺は一身の気を主り、華蓋といわれており、脾気虚弱では脾の運化が失調し、その結果肺気不足になって、息切れ、喘息、ひどい場合は浮腫などの症をひき起こす。
臨床上、脾胃虚弱では営養障害を起こし、抗病力の低下がよく見られる。また脾気虚は肺病の回復に影響し、食欲不振、下痢、消痩、顔色蒼白い、身体倦怠、咳嗽などの脾虚によって肺を養えない証候が現れる。肺気虚衰の場合は、水谷の精微を輸布できなくなって、中焦が営養を失い、また脾気が虚す。
水液代謝(図E−6)
脾は水湿の運化を主り、肺は宣発粛降を主り水道を通調し、脾と肺は共同して水液の代謝を行っている。それ故、脾肺に異常が生じると相互に影響する。
脾の機能が失調すると水湿の運化がよくいかなくなり、水湿が内停して痰飲を生じ、肺の宣降作用に影響を及ぼして咳喘が発生する。病は肺にあるが、その根本は脾にある。したがって「脾は生痰の源、肺は貯痰の器」といわれる所以である。
肺病が長くなると脾に影響を与える。肺気の虚衰では宣降作用が失調し、水液代謝不利をひき起こして湿が中焦に停留し、脾陽(脾の働きのもと)が影響を受けて、その働きを自在に発揮できず、身体倦怠、水腫、腹脹、下痢などの症が現れる。
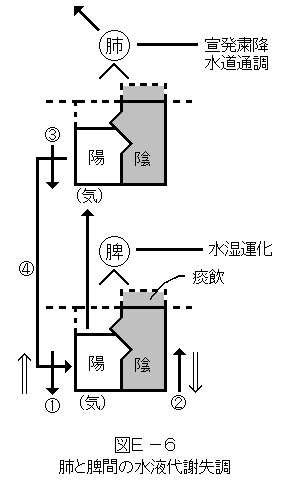
8.心と肺
心肺とも上焦に位置し、心は血を主り、肺は気を主っており、両者の間は気と血の関係である。気は陽に属し血は陰に属し、血の運行は気の推動に依存しており、気は血に載っかって二者協同して全身を行っている。
もし血があって気の推動がなかったら、血は凝固して行らなくなり、淤血となってしまう。もし気があって血がなかったら、気は寄り附き載っかるものがなくなり、散り散りバラバラに拡散してしまう。
したがって「気は血の帥となす」、「気は血の母」、「気行れば血行る」、「気滞れば血滞る」などといわれている。
病理上、次のいくつかの型がよく見られる。
心肺気虚
一臓が気虚になると別の一臓も気虚になる。肺気の虚弱では宗気不足を起こし、心気もまた虚弱になる。心気虚になると、心血が肺を充養できなくなり肺気も虚して、その結果心肺気虚を起こす。この場合、動悸、息切れ、咳喘、胸悶、乏力、自汗などの症がみられる。
気虚血淤
心肺気虚では気虚が血淤を起こし、心血淤阻して心胸痛、肺が粛降を失して咳喘を生じる。
心火が肺を灼傷する
心火が亢盛して肺陰を灼傷し、いらいら、不眠、咳嗽、喀血を起こす。
心包に逆伝する
温病<ウンビョウ>の発展過程で病邪がひどいとき、変化が迅速で正規の伝変順序を経ないで、心気を通り越して直接心営に突入する。いわゆる「心営に逆伝する」である。
衛 → 気 → 営 → 血
(表)−−−−−−↑−→(裏)・・・一般的伝変の順序
└───→───┘
昏睡、うわごとをいうなどの中枢神経の症状が現れる。
※温病については後述する。
9.心と肝
心と肝の関係は血液と精神の二方面である。
血液関係
心は一身の血液運行の中枢で、肝は血液の貯蔵と調節を主り、二者協同して血液の循環を行っている。心血不足あるいは肝血不足になると、二者は互いに影響し合って心肝血虚となり、動悸、顔色つやがないなどの心血虚証、更にめまい、爪の異常、手足のふるえなどの肝血虚証が見られるようになる。
精神関係
心は精神意識を主り、肝は疎泄を主る。人の精神活動は主として心が主宰しているもので、肝とも密接な関係をもっている。
肝気の疎泄機能が正常であれば、気の働きも順調で気血は平和で、心情もおだやかである。心と肝はともに血の充養に頼っており、精神面の変化異常でも心肝同じような影響を受ける。肝血不足の病人では、めまい、爪の異常と同時に、不眠、多夢、動悸、不安などの心の病症がみられる。
心陰不足で虚火亢盛のものでは、いらいら、動悸、不眠、多夢と同時に、いらいらして怒り易く、めまい、目の充血などの肝病の症状が現れる。
心陰不足 → 虚火亢盛 → 肝陽上亢
10.肺と肝
肺は気を主りその性質は粛降であり、肝は血を蔵しその性質は昇発である。このようなことから肺と肝の関係は、人体の気の昇降運動の機能ということができる。
肺と肝の間は、肺は全身の気の調節を主っており、肝は全身の血の調節を行っている。肺の全身の気の調節機能は血の充養に頼っており、肝の全身にわたる血液輸送はまた肺の気の推動に依存している。いいかえると肝の疎泄作用によって肺気は順調にめぐり、また全身に津液を輸布させることができる。肺の津液輸布の正常な働きによって肝はその剛性を柔軟にさせ、肝気を伸展させることができる。肺気虚弱になると、肝の調節や疎泄機能に影響を与えて(たとえば肝気鬱結)、身体乏力、息切れ、精神抑鬱などの症が現れる。
肺の粛降機能が失調すると、肝の昇発太過が起こり、咳嗽、胸脇痛、胸脇脹満、頭痛、めまいなどの症をひき起こす。肝気鬱結すると、「気鬱すれば熱を生ず」といわれるように、熱と化して(寒と化す場合もある)肝火亢盛し、肺陰を灼傷して肺の調節粛降に影響を与え、咽喉痛、咳痰、喀血などの症が現れる。これを「肝火犯肺」、「木火刑金」、「木扣金鳴<モッコウキンメイ>(木を叩くと金が鳴く)」という。(図E−7)
肝は昇発を主る
肝は血量を調節する機能があり、その経脈は上の頭部から脳に絡んでいる。肝機能の正常時には、春季の樹木のように生気が満ち溢れてすくすくと伸びやかである。このようなさまを「昇発」という。昇発が太過になると肝陽上亢し、頭痛やめまいなどの証候が起こってくる。
肝は剛性である
肝は「将軍の官」といわれており、剛とは堅い、強情という意味である。肝は条達のびやかを喜び抑鬱を悪み太過を嫌い、肝の剛臓たる所以である。このような性質は主に肝気の面で顕著で、精神の刺激を受けると肝気太過では、いらいら、怒り易いなどの症が現れ、反対に肝気不足になると恐れる症が現れる。