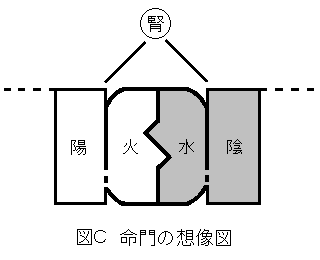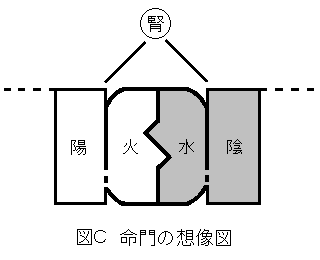
命門学説によれば、五臓六腑の五臓では各臓は心、肝、脾、肺、腎それぞれ一つであるが、腎に限っては二つあるといわれている。その二つの腎の中の命門は生命の根源、生命の根本、先天の気が宿る所、人体の生化機能の根源が存在するところと述べられている。
昔から部位と機能についてはいろいろの説が述べられているが、現在に至るも統一された認識はなされていない。
《難経・三十九難》にはじめて腎の左右にふれ、「左は腎であり、右は命門である。命門は精神の宿るところであり、男子では精気を蔵し、女子では子宮につながり、命門の気は腎と通じている」とある。「命門の気は腎に通ず」とは、腎と命門は左右に別れているが、実際には往来する道があるということである。
宋代の陳言は、彼の著した《三因極−病証方論》の中で「古人のいう左腎とは腎臓であり、その腑は膀胱である。右腎とは命門であり、その腑は三焦である」といっている。厳用和も「左は腎経であり、右は命門である」と説いている。
以上の引用からすれば、《難経》の時代(張仲景《傷寒論》以前)から宋代まで(1200年前後)は、左は腎、右は命門という説が主流を占めていた。
明代には、李時珍、張景岳、趙献可、李梃、虞摶(虞天民)などが命門に対して特別に論述を行っている。彼等は命門の実質と位置について、ある者は《難経》の左腎右命であるといい、ある者は両腎の間にあるといい、ある者は両腎の総称であるといっている。明代以降は、両腎の間にあるというのが定説になっている。これらの論争は臨床上あまり価値がなく、重要なのは命門の作用である。
明代の学者は、命門は水谷の運化、気血津液の輸布と転化などの源動力、臓腑経路の機能、つまり人体における生化を行う「相火」<ショウカ>の作用を主っているものと考えている。
李時珍は「命門は精を蔵し、胞に系<カカ>るものである・・・下は二腎に通じ、上は心肺に通じ脳を貫く。生命の源であり、「相火」の主、精気の腑である。人の生まれ、物の生ずるのは、みなここより出づ」といっている。
趙献可は《医貫・内経十二官論》で命門は「真君真主である」、「腎ここになければ、筋骨脆弱、精神痿微。膀胱ここになければ、三焦の気、化せず、水道行らず。脾胃ここになければ、水谷を蒸腐する能わず、五味出でず。肝胆ここになければ、肝の疎泄作用に影響を及ぼし、精神活動に異常を生ずる。大小腸ここになければ、変化行われず、大小便閉す。心ここになければ、精神昏迷し、万事に応ずる能わず」と述べている。
彼は、人体の生理活動は片時も止まることを知らず、休むことなく廻り続ける走馬燈のようなもので、命門の「相火」は燃えているローソクの火のようなものである。中のローソクの火が消えると走馬燈は止まってしまう。命門の「相火」が消えると生命は終わって死んでしまうといっている。
また張介賓は《類経附翼・求正録》で、「命門は両腎を総括し、両腎は命門に属する。故に命門は水火の家、陰陽のいる所、精気の海、生死の孔である。もし命門が虚損すると、五臓六腑を面倒をみることができなくなって、陰陽に病変が起こる」。このように命門を水火の腑、陰陽の海といい、趙献可は真水をも同時に含むといい、李時珍は精気の腑といい、命門は火を主るだけでなく水も主っているといっている。水を主る、精を蔵すというのは腎本来の作用である。命門には火と水が同居しており、命門の火は生化の源である。