相生<ソウジョウ>と相克<ソウコク>
相生(図B−1)
相生とは相互に生む、促進するという意味である。五行の相生関係とは水は木を生ずる、木は火を生ずる、火は土を生ずる、土は金を生ずる、金は水を生ずるというものである。
たとえば、木は火を生ずる、火は土を生ずるで、我がいま火とすると、木は我を生ずるものであり、土は我が生ずるものということになる。他の四行でも同様の関係が成り立つ。
五行の相生関係は、古代からの長い経験から生まれたものであり、樹木の成長には水の灌漑が必要であり、水は樹木の成長を助けており、いわゆる水は木を生ずる。木材は燃えて火を生ずる。故に木は火を生ずる。灰は土に変わる故に火は土を生じる。金属類は地中に埋蔵されている。だから土は金を生ずる。夏を過ぎると秋になる。秋季は次第に寒くなって、きびしく冷徹の状態になり、すべての物が寒い冬に備えて収蔵の体制に入る。つまり、金(秋)は水(冬)を生じる。- 相生の順序
- 木 → 火 → 土 → 金 → 水 → 木
- 肝 → 心 → 脾 → 肺 → 腎 → 肝
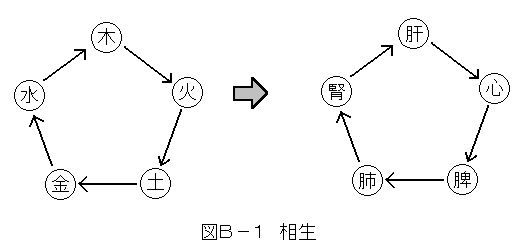
相克(図B−2)
相克関係も相生関係と同様に、昔からの生活上の経験から編み出されたものである。
相克とは相互に抑制し合う意味である。物事が運動発展していく過程中にあって、促進する要素と抑制する要素とがある。
五行中の相生の関係は有利に働く促進する要素であり、相克は抑制、拮抗する要素である。
この相克という機能が具っているから、物事の発展、進行過程において異常に発展し過ぎ収拾できなくなるという事態が発生しなくてすむ。人体は、このような相生と相克という関係があってはじめて健康を維持していくことができる。
水は火を消すことができるし、火の勢いが過盛にならないように抑制する。故に水は火を克するという。金属は硬いが火力によって軟化させることができる。故に火は金を克するという。金属で作った道具(たとえばノコギリ)は樹木を切り倒したり、また色々と工作するのに使用される。故に金は木を克する。
樹木は地中深く根をおろし、そのさまはちょうど土に突き刺さったように立っている。それ故木は土を克するという。川や池は土提によって堰き止められ、氾濫や洪水を防いでいる。したがって土は水を克する。- 相克の順序
- 木 → 土 → 水 → 火 → 金 → 木
- 肝 → 脾 → 腎 → 心 → 肺 → 肝
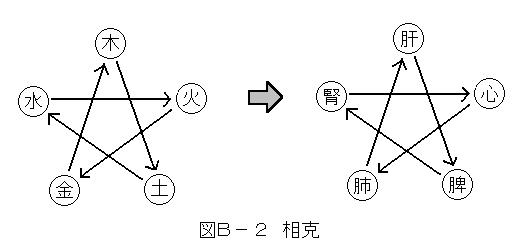
以上、相生と相克を別々に述べてきたが、これら二つには実際は密接な連係があり、相互に依存し合っている。相生と相克という矛盾した二つが一体となって健康を保っている。
もし相生があって相克がなかったなら、強いものは無制限に強くなり、弱いものはますます弱くなり、偏盛あるいは偏衰になってしまう。
反対に、相克だけあって相生がない場合は、成長促進の源がなくなってその結果は想像にかたくない。
このように、相生と相克は同時に存在して、太過または不及にならないように、一定の範囲内で正常に発展するように作用している。(図B−3)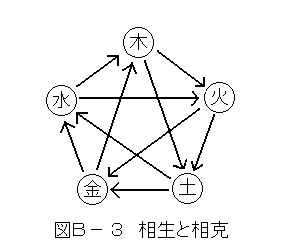
五行中での一行はみな生と克という二つの矛盾した機能をもっていることは前に述べたが、相生にあっては「我が生ずる」、「我を生ずる」、また相克では「我が克する」、「我を克する」の作用である。この四者は連係して完全な統一体を形成している。たとえば、木(肝)は土(脾)を克し、火(心)は土(脾)を生じ、土は(脾)は金(肺)を生じ、金(肺)は木(肝)を克する。 したがって木(肝)は土(脾)の働きを抑制するが、片一方で火(心)は土(脾)の働きを促進し、土(脾)の働きが旺盛になって木(肝)の過分の抑制を受けなくなる。
また土(脾)が旺盛になると金(肺)の働きが活発になり、必然的に金(肺)が木(肝)を克するようになり、木(肝)は金(肺)の制約を受けてやたらに土(脾)を克するようなことはなくなる。
その他の四行でも同じことが行われ、五行の間の依存関係は縦横に交錯し複雑にかつ系統立って連係し、発展運動を続けている。
人体では以上のような相生と相克という作用が一体となって健康を維持している。木における相生と相克の関係を図示する。(図B−4)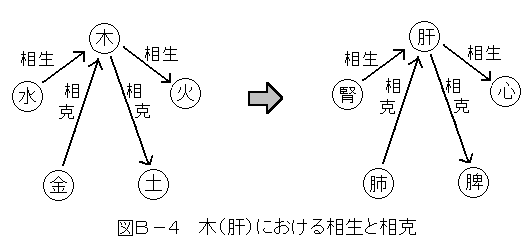
相乗<ソウジョウ>と反侮<ハンブ>
五行中の太過とは、ある一行が偏盛した状況で、不及とは五行中のある一行が偏衰した状況であり、この場合(図B−5)、(図B−6)、(図B−7)のように相乗と反侮が同時に起こる。
乗とは虚に乗じて相手方に侵襲することで、侮とは自分より強い相手をあなどることであり、五行間で異常現象が起こった状況である。
前に述べた五行間の相克関係、「木(肝)は土(脾)を克する、土(脾)は水(腎)を克する、水(腎)は火(心)を克する、火(心)は金(肺)を克する、金(肺)は木(肝)を克する」は、一般に五行の各行の間は正常で調和して発展運行している状況である。
しかし異常な状況下では、五行間の調和が破れて、量的な面で変化が発生し、このような相乗反侮という現象が出現する。
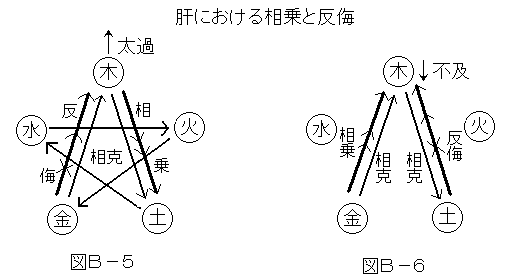
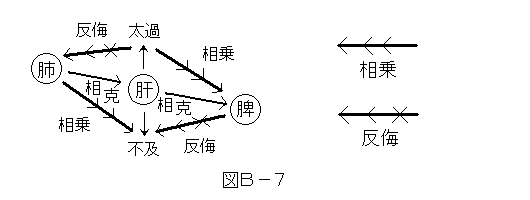
では、反侮とはどのような場合をいうのだろうか?
正常な状況では水は火を克するが、水、火の間の量的面での変化が起こったとき、必ずしも水は火を克するとは限らない。
たとえば、水が大変少なくて火が燃え盛っている場合、ちょうどバケツ一杯の水で山と積まれた薪の火を消そうとしても消えないばかりか、燃え盛る火のために水は蒸発してしまう。このような火が水を克するという状況が反克すなわち反侮である。(図B−8)
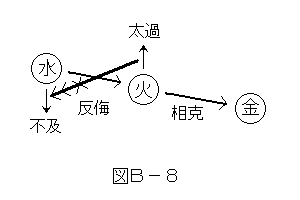
相乗と相克は似ている。たとえば、火が金に乗ずる、金が木に乗ずる等は相乗というが、性質上相乗と相克は全く異なっている。相克は一般に正常な状態のとき起こるもので、互いに一行と他の一行が制約関係にある。
しかし相乗はそうではなく、往々反侮と同時に現れるもので、明らかに一種の異常現象である。火が燃え盛り水が少ないときは、水は火の旺盛を制約することができず、これによって火は金に大損害を与えてしまう。(図B−9)
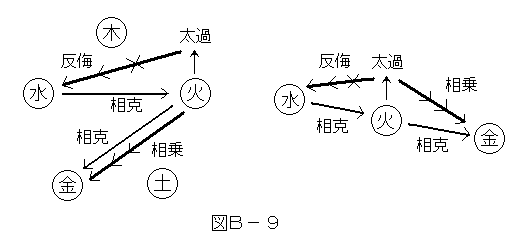
勝復(図B−10)
勝復とはどういうことだろうか?
勝とは広い意味で相乗のことで、復とは報復つまり仕返しすることである。木が不及になると金が木に侵襲して相乗が起こる。この時点が勝に当る。
木が鬱すると火が生じ、火は金を克する。この時点までが復に当る。
勝復の一般的な決まりは、勝があればその後に必ず報いすなわち復がくるというものである。
昔の人は自然気候の循環の現象に用いたが、その後疾病の流行の推測や予後、治療関係にも用いられるようになった。
自然界を例にとってみると、雨が長く続いて気温が上がらないのは、五行学説からいえば、水が火に勝つ、水が火に乗ずるということである。
しかしある程度した後は必ず反対方向へ転化が起こり、一変して長い間雨が降らず気候は熱に転じる。このような現象を五行学説では勝復といい、自然界の気候の自動調節の表れであり、一切の変化の発生は、五行間のこのような働きによっていつまでも続き止まない。
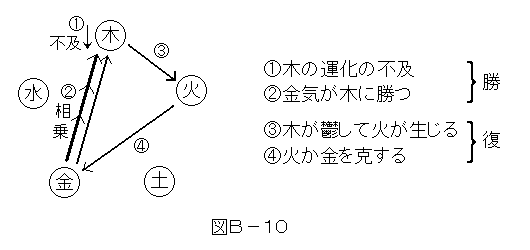
「亢すれば害し、承すれば制す、制すれば生化す」
五行間には相生と相克の関係があるが、相克は五行間の相互制約を行っており、これは物事が成長発展変化していく過程での、五行間の相互対立の両方間の闘争と考えてよく、相克関係が正常に運行してはじめて物事は順調に進行していく。
《素問・六微旨大論》に「亢すれば害し、承すれば制す、制すれば生化す」とある。つまり「承すれば制す」とは五行間の相互制約で、「制すれば生化す」とは五行間の相互制約という状況下ではじめて正常な成長変化が生まれることを指している。制とは克のことで、物事が成長変化していく上での決定的役割を果たしている。
五行学説では、このような制約現象が、休むことなく五行間の盛衰につれて行われていると考えられており、それによってたゆまざる成長発展がなされている。
五行間の運動は、五行間の盛衰の流れの結果起こる。「亢」とは高ぶる、過大になるという意味で、五行間の運動の盛衰の結果起こるものであり、盛衰がなかったら運動も変化もあり得ない。
ここで問題なのは亢の程度であり、亢が制約抑制を受けることができる程度であれば、正常現象の相克ということができる。
亢が制約を受けることのできる範囲を超えて亢盛している場合は、これを制約することができなくなって、五行の間に異常な現象の相乗や反侮が現れる。それ故、亢が制約できない位過大になると五行間に異常な現象の相乗や反侮が起こって、正常な生化が行われなくなる。